探究と情報をつなぐ(1)〜SSH指定校としての「データ駆動型探究」に向けた実践〜
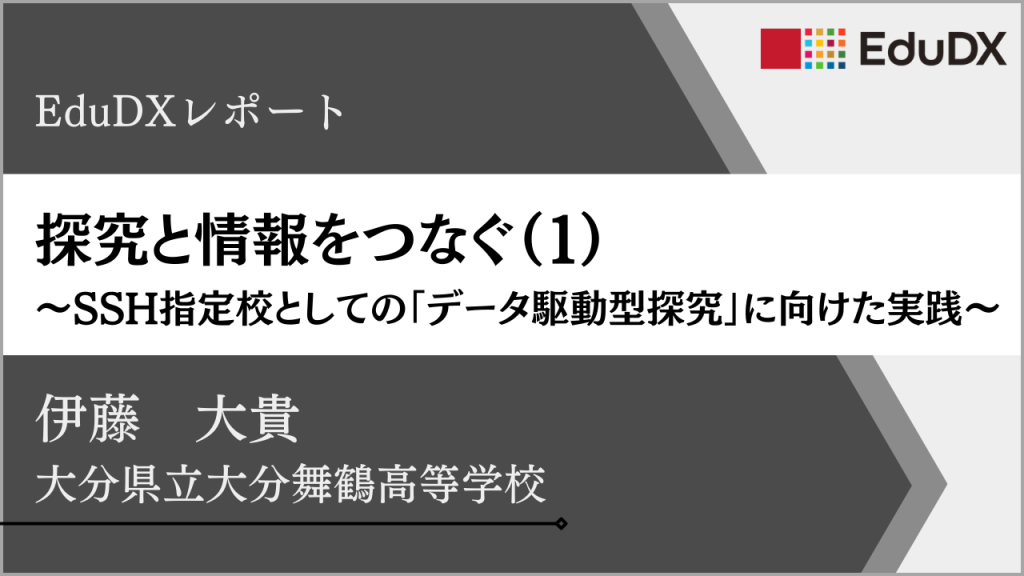
2024年8月29日 伊藤 大貴(大分県立大分舞鶴高等学校)
1.総合的な探究と総合的な学習
「探究」という言葉が教育業界に浸透して数年経った。この言葉は、学習指導要領の改定により、広まったものである。具体的には、従来小学校〜高等学校において設定されていた、「総合的な学習の時間」が、2018に告示された改定により、「総合的な探究の時間」へと変容したものである。この「学習」と「探究」の大きな違いは、取り組む児童・生徒の「主体性」である。「平成27年度学習指導要領実施状況調査(高等学校 総合的な学習の時間)」によれば、「⑴自分で課題を決めて,解決に向けて取り組んでいる」等といった全ての質問項目において、学校種が上がるほど肯定的な回答の割合が低くなっていることが示されている。つまり、小・中学校の取組の成果の上に高等学校にふさわしい実践が十分展開されているとは言えない状況であったことが指摘されている。私自身、高校時代の「総合的な学習の時間」に何を行っていたか覚えておらず、記憶に残らない活動であったことが伺える。
なぜ高等学校における「総合的な学習の時間」が十分に展開されなかったのか、その理由は一つではない。特に、課題のテーマ設定や、生徒自身による主体的な問題解決活動を教員がどのように支援するかという点は、当時も現在も共通する課題である。これらの課題に対して、当時は「道具や環境」の面でも制約があったことが一因であると考えられる。当時は、現在のように1人1台端末も整備されておらず、文献やテレビなど、限られたメディアをもとに「調べ学習」を行うことが多かった。もちろん、その中でも探究的に深めることは可能であったが、インターネットが現在のように使える環境ではなかったため、テーマに関する幅広い知識を獲得したり、問題を洗い出し、解決に向かう手立てを追求したりすることが困難であった。このため、私自身も興味や関心を追求しようと思えなかったのである。 しかし、現在はインターネットやICTが普及し、その活用がこれらの課題解決の糸口になり得る。1人1台端末も整備が整備され、調査できる文献や使用できるツールも充実してきた。ハードウェア的な環境で言えば、私が高校生の頃と比べ、著しい変化が起こっている。
表1 学習指導要領の新旧比較
| 総合的な探究の時間 | 総合的な学習の時間 | |
| 学習の目的 | 自分の生き方だけでなく在り方について考えながら課題を発見して解決する能力を養う | 自分の生き方について考えながら課題を解決する能力を育成する |
| 課題解決のプロセス | 生徒が自ら解決したいと思う課題に出会い、その課題解決に取り組む | 教員がテーマを設定し、生徒が課題解決をする |
| 学習の重点 | 自己の在り方生き方を考えながら、課題発見する | 課題解決の過程で自己の生き方を考える |
しかし、表1のように、学習指導要領を比較すると、現在の学習指導要領における「総合的な探究の時間」においては、「主体性」が重要視されており、「総合的な探究の時間」は、生徒が自ら課題を発見し、解決に取り組むことが求められている。そのため、私達教員に求められる支援も「コーディネート」より「ファシリテーション」のウェイトが大きくなっている。
2.探究と情報教育の関わり
では、どのように課題の発見や解決に取り組むのか、そこで、1人1台端末の活用が重要であると考えられる。もちろん、書籍から情報を得るのは重要であり、そのようなリソースから得られる情報の信頼性の理解については、初等中等教育段階で身につける必要がある。しかし、「問題を探す」「先行研究を探す」というような場面においては、1人1台端末を活用することで、効果的に情報を探索することができる。また、探究を行う「場所」は様々であることも踏まえ、インターネットを活用した情報収集に大いに貢献できると考えられる。
このようなICTの活用は、情報の収集だけでなく、処理や表現においても重要な役割を持っている。例えば、アンケートを作成し、得られたデータから統計的な処理を行う場面においても、コンピュータが必要になる。最近では、Google FormsやMicrosoft Formsなどのサービにより、電子的な調査を行うことができるほか、分析においてもExcel等の統計ツールを使用することで、効率的・効果的な探究活動を行うことができる。もちろん、「時間をかけない探究」というわけではないが、事実上、学校が探究の時間として設定できる時間は「週に一時間程度」であることが多く、1人1台端末をはじめとしたICTの活用は必須であると考えられる。そのため、これらのツールの使い方やデータ処理の方法等も学ぶ必要がある。
3.探究と情報科の関わり
探究を深めるための知見として、高等学校情報科での学びは重要である。新学習指導要領における「情報Ⅰ」「情報Ⅱ」は問題解決を軸に、情報学を実践的に学ぶ科目である。具体的には、情報Ⅰは、「第1章 情報社会の問題解決」「第2章 コミュニケーションと情報デザイン」「第3章 コンピュータとプログラミング」「第4章 情報通信ネットワークとデータの活用」の4つの単元から成り立っており、それぞれの単元に問題解決や探究において重要な要素が含まれている。特に、情報Ⅰの「第1章 情報社会の問題解決」「第2章 コミュニケーションと情報デザイン」は,探究学習における「課題の発見」「解決策の立案」と対応しており,「第3章 コンピュータとプログラミング」「第4章 情報通信ネットワークとデータの活用」の2つの単元は探究の手法を学ぶうえで役立つ要素が多く、「データの活用」における統計的な手法は、様々な分野の探究に応用することができる。
「データの活用」については、統計・データサイエンスに関する分野が充実しており、統計指標や集計方法に加え、回帰分析や仮説検定など、アカデミックなスキルを学ぶことができるため、科学的な根拠としての「データ」を処理することで、信頼性の高い探究を行うことができると考えられる。 次回は、実際に「情報Ⅰ」や「情報Ⅱ」で学ぶ手法を用いたデータ分析について述べる。
